| 紹介図書目録 | |
ジュゴン
|
|
その他
|
|
| B412 沖縄・琉球民族 沖縄と自然はこちら | |
| B910 ヤギさん関連図書はこちら | B920 アホウドリさん関連図書はこちら |
| 分類表に戻る | |
| 図書紹介 留意事項 |
その他
| 書名: ガイドツアー複雑系の世界 サンタフェ研究所講義ノートから 原書名:COMPLEXITY:A GUIDED TOUR |
No.B520018 NDC 404 |
| 著者・出版社: ミッチェル,メラニー、高橋洋【訳】/紀伊國屋書店 |
初版2011/12/07 ¥3,360 |
| 内容: ヒトの脳に存在する何兆ものニューロンという「物質」は、いかに「意識」のような複雑な現象を生みだすのか?免疫系、インターネット、国際経済、ヒトのゲノム―これらが自己組織化する構造を導いているものは何か?一匹では単純に振る舞うアリが、グループを形成すると、ある目的のために統率された集団行動がとれるのはなぜか?第一線の研究者を案内人として、その広大で魅力的な世界を訪ね巡る、本格的入門書。 【著者からのコメント】 本書に取り上げてきた科学の多くはまだ産声を上げたばかりだが、かくも野心的な目標を実現するという将来の展望があるからこそ、複雑系は真に魅力的な研究分野だといえる。そして一つ確実にいえることがある。どんな偉大な科学の場合にも当てはまるが、これらの目標を追求するには、主流科学から定義のはっきりしない未踏の領域に分け入ることによって、被るかもしれない失敗や非難をいとわずに挑戦する意欲と、冒険的な知的精神が必要である。作家で冒険家のアンドレ・ジッドの言葉を借りれば、「新たな土地を発見するためには、いったん海岸線から離れなければならない」のだ。読者の皆さん! ともに複雑性の新たな大地を探検できる日がいつかやってくるのを心待ちにしながら、ここに本書を閉じることとする。 (本文第19章末より) 第1部 背景と歴史 第1章 複雑性とは何か? 昆虫のコロニー/脳/免疫系/経済/ワールドワイドウェブ/ 「複雑なシステム」に共通する性質/複雑性はどのようにして測れるのか? 第2章 力学、カオス、そして予測 力学系理論の起源/予測についての新たな見方/線形ウサギと非線形ウサギ/ ロジスティック写像/カオスのなかの普遍性/カオスに基づく革新的な考え方 第3章 情報 情報とは何か?/エネルギー、仕事、エントロピー/マクスウェルの悪魔/ 統計力学の概略/ミクロ状態とマクロ状態/シャノンの情報 第4章 計算 計算とは何か? 何が計算可能なのか?/ヒルベルトの問題とゲーデルの定理/ チューリングマシンと計算不可能性/ チューリングマシンとして定義された一定の手続き/万能チューリングマシン/ チューリングの決定問題の解決方法/ゲーデルとチューリングが歩んだその後の道 第5章 進化 ダーウィン以前の進化の概念/ダーウィンの理論の起源/ メンデルと遺伝のメカニズム/現代の総合/現代総合説への挑戦 第6章 初歩の遺伝学 DNAの仕組み 第7章 複雑性の定義と測定基準 複雑系の測定基準――サイズ/エントロピー/アルゴリズム情報量/論理深度/ 熱力学深度/計算能力/統計的な複雑性/フラクタル次元/階層度 第2部 コンピューター上の生命とその進化 第8章 自己複製するコンピュータープログラム 生命とは何か?/コンピューター上での自己複製/ 自己複製コンピュータープログラムのより深い意味/DNAにおける自己複製/ フォン・ノイマンの自己増殖オートマトン/ジョン・フォン・ノイマン 第9章 遺伝的アルゴリズム 遺伝的アルゴリズムのレシピ/現実世界の遺伝的アルゴリズム/ 進化する空き缶おそうじロボット「ロビー」/ GAによって進化した戦略はいかにして課題を解決したか?/GAによる進化の経過 第3部 拡張される計算 第10章 セル・オートマトン、生命、そして万能計算 自然界の計算/セル・オートマトン/ライフ・ゲーム/四つのクラス/ ウルフラムの「新しい科学」 第11章 粒子による計算 第12章 生物系における情報処理 情報処理とは何か?/免疫系/アリのコロニー/生物代謝/ これらのシステムの情報処理 第13章 コンピューター上で類推を実現する 簡単なことは難しい/類推する/私のたどった類推への道/単純化された類推/ 模倣者たれ/正しい模倣の仕方/コピーキャットプログラムの概要/ コピーキャットの実行/要約 第14章 コンピューターモデリングの展望 モデルとは何か?/概念モデル/協力関係の進化をモデル化する/ モデリングの展望/コンピューターモデリングの注意点 第4部 ネットワーク思考 第15章 ネットワークの科学 狭い世の中/ネットワークの新しい科学/ネットワーク思考とは何か?/ それでは「ネットワーク」とはいったい何か?/スモールワールドネットワーク/ スケールフリーネットワーク/ネットワークの耐障害性 第16章 現実世界へのネットワークサイエンスの適用 現実世界のネットワークの例/ネットワーク思考の意義/ スケールフリーネットワークの起源/べき乗則とそれに対する疑問/ 情報の伝播とネットワーク障害の連鎖 第17章 スケーリングの謎 生物学におけるスケーリング/学際的な協力/べき乗則とフラクタル/ 代謝スケーリング理論/代謝スケーリング理論の持つ可能性/批判/ べき乗則の未解決の謎 第18章 複雑化する進化の理論 遺伝学の複雑化/遺伝子とは何か?/エボデボ/ 遺伝的調節とカウフマンの「秩序の起源」/カウフマンの理論に対する反応/要約 第5部 結論 第19章 複雑性の科学の過去と未来 統一理論と一般原理について/複雑系研究の起源/五つの問い/ 複雑性の未来、あるいはカルノーを待ちながら 訳者あとがき 図版クレジット 参考文献 原注 索引 ミッチェル,メラニー[ミッチェル,メラニー][Mitchell,Melanie] ポートランド州立大学教授(コンピュータサイエンス)。サンタフェ研究所客員教授。ミシガン大学博士課程在籍中、師ダグラス・ホフスタッター(『ゲーデル、エッシャー、バッハ』著者)の指導の下、人間の類推機能を模倣するコンピュータープログラム「COPYCAT」を共同開発する。英米で評価の高い『ガイドツアー 複雑系の世界』は、2009年のアマゾン・コム科学書ベスト10、2010年に英国王立協会推薦科学図書として選ばれ、同年のファイ・ベータ・カッパ・クラブ(全米優等学生友愛会)科学図書賞を受賞した 高橋洋[タカハシヒロシ] 同志社大学文学部文化学科哲学及び倫理学専攻卒。IT企業勤務を経て翻訳家 |
|
| メモ: |
|
ページのはじめに戻る
| 書名: いま自然をどうみるか (新装版) |
No.B520017 NDC 404 |
| 著者・出版社: 高木仁三郎/白水社 |
初版2011/05/10 ¥2,100 |
| 内容: 数多くの紙誌から絶賛された根源的エコロジズムの記念碑的名著。現代の危機を解く自由と開放の自然観に基づきつつ、新たな地球像と人間の生き方を探り、技術文明の一大転換を訴える。 「大方の批判とは逆に、まさにこの人間の自由と解放という点にこそ、私はエコロジズムに大きな可能性をみたい。つまり、単純に自然の全体の中に人間を埋没させることとしてでなく、人間の精神を広大なる自然へ向かって解放するかたちで人間を相対化するものとして、エコロジー的な自然と人間の関係を構想したい。この相対化は、二元化された自然像から私たちを解き放ち、根源的な自然と人間の関係を復権させしめるだろうから、それにより私たちは、より解放的で創造的な地平へと到達できるだろうと、期待されるのである。」(本文より) 序章 いまなぜ自然か 第一部 人は自然をどうみてきたか 第一章 ゼウスとプロメテウス 1 プロメテウス神話 2 ヘシオドスの世界 第二章 ロゴスとなった自然 1 宇宙大の動物 2アリストテレスの宇宙 第三章 機械としての自然 1 解放の時代 2 近代的自然観へ 3 ニュートンのもたらしたもの 第四章 宇宙は解けたか 1 数学的宇宙 2 宇宙と人間 第二部 いま自然をどうみるか 第五章 エコロジー的地球像 1 宇宙船「地球号」モデル 2 開放定常系のモデル 3 ガイアのモデル 4 生物と文化 第六章 民衆の自然 1 先住の世界から 2 近代を超える精神 第七章 自然と労働 1 自由の国・必然の国 2 労働と生活 終章 自然に生きる 増補 そしていま、自然をどうみるか 1 激動の時代の中で 2 根源的転換に向けて 高木仁三郎[タカギジンザブロウ] 1938年生。1961年東京大学理学部科学科卒。東京大学原子核研究所助手、都立大学理学部助教授などを経て原子力資料情報室代表となる。1997年、長年の反原発・反核活動に対してライト・ライブリフッド賞を受賞。2000年逝去。 |
|
| メモ: |
|
ページのはじめに戻る
| 書名: 動的平衡 生命はなぜそこに宿るのか |
No.B520016 NDC 404 |
| 著者・出版社: 福岡伸一/木楽舎 |
初版2009/02/25 ¥1,600 |
| 内容: ハカセ、生きてるってなんですか?生命現象の核心を解くキーワード、それは<動的平衡>(dynamic equilibrium)。哲学する分子生物学者・福岡伸一が問う生命のなりたち、ふるまい、ありよう。「人間は考える管である」「なぜ、あなたは太り続けるか」「ES細胞は再生医学の切り札か?」「種を超えるウイルス」「アンチ・アンチ・エイジング」ほか、10年におよぶ画期的論考をすべて収録。「生命の流れ」を、流麗な文体で語る福岡生命理論の決定版! プロローグ 生命現象とは何か 第1章 脳にかけられた「バイアス」―人はなぜ「錯誤」するか 第2章 汝とは「汝の食べた物」である―「消化」とは情報の解体 第3章 ダイエットの科学―分子生物学が示す「太らない食べ方」 第4章 その食品を食べますか?―部分しか見ない者たちの危険 第5章 生命は時計仕掛けか?―ES細胞の不思議 第6章 ヒトと病原体の戦い―イタチごっこは終わらない 第7章 ミトコンドリア・ミステリー―母系だけで継承されるエネルギー産出の源 第8章 生命は分子の「淀み」―シェーンハイマーは何を示唆したか 福岡伸一[フクオカシンイチ] 1959年東京生まれ。京都大学卒。米国ロックフェラー大学およびハーバード大学医学部博士研究員、京都大学助教授を経て、青山学院大学理工学部教授。分子生物学専攻。専門分野で論文を発表するかたわら一般向け著作・翻訳も手がける。2006年、第1回科学ジャーナリスト賞受賞。著書に、『プリオン説はほんとうか?』(講談社ブルーバックス講談社出版文化賞科学出版賞)、『生物と無生物のあいだ』(講談社現代新書2007年サントリー学芸賞)など。 |
|
| メモ: |
|
ページのはじめに戻る
| 書名: 岩波科学ライブラリー フジツボ 魅惑の足まねき |
No.B520015 NDC 485.3 |
| 著者・出版社: 倉谷うらら/岩波書店 |
初版2009/06/24 ¥1,575 |
| 内容: 泳ぎ、歩き、逆立ちし、慎ましく脱ぐ。つぶらな瞳と招く脚―。ダーウィンが愛した魅惑の生物、その殻に隠された素顔がいま明らかに。人体に生えるって本当?東郷平八郎がバルティック艦隊に勝ったのはフジツボのおかげ?なぜ歯医者さんが注目?美しい写真や歴史的な博物画も満載。巻頭に図鑑、巻末に観察ガイドとペーパークラフト、そしてページ右下に変態パラパラ付き!充実のオールカラー版。 1 エビ、カニ、フジツボ 貝なのか? あぁ、あなたは甲殻類―殻のつくり ほか 2 浮世離れなF生活 足でお食事 こっそりと脱ぐ ほか 3 ダーウィンの「愛しのフジツボ」たち やはり載るのは貝の図鑑? 八年間のF時代 ほか 4 文化とのつながり 江戸時代の本草画とF 藤壷と夕顔 ほか 5 偉大なる付着生物 汚損生物としての歴史 フジツボ海戦 ほか 倉谷うらら[クラタニウララ] 愛知県生まれ。ウェールズ大学バンガー校海洋科学学部海洋生物学科卒業、同大学博士課程中退。東京大学三崎臨海実験所での実験補佐、日本動物学会の職員を経て、海洋生物研究家。所属団体は、日本付着生物学会、日本動物学会、日本古生物学会、日本湿地ネットワーク、海の生き物を守る会。 |
|
| メモ: |
|
ページのはじめに戻る
| 書名: 岩波科学ライブラリ− 日本の動物はいつどこからきたのか 動物地理学の挑戦 |
No.B520014 NDC 482 |
| 著者・出版社: 京都大学総合博物館/岩波書店 |
初版2005/08/04 ¥1,260 |
| 内容: 1. 謎解きトシテノ動物地理学 2. 島嶼が多様性を花咲かせる 小さな島々のヘビ、琉球列島のカエル、伊豆半島のトカゲ 3. 列島内での分化と動物たちの移動 小型サンショウウオ、ケモノ、ビワコオオナマズ 4. 昆虫の起源と多様性 ハンミョウ、ネクイムシ 5. 海流が生み出した謎 アサリ、ハマグリ 6. 絶滅した動物たち ニホンオオカミ、小笠原諸島 7. 動物地理学の未来 |
|
| メモ: |
|
ページのはじめに戻る
| 書名: 岩波新書 354 孤島の生物たち ガラパゴスと小笠原 |
No.B520008 NDC 468.000 |
| 著者・出版社: 小野幹雄/岩波書店 |
\650 |
| 内容:
大洋のなかにポツンと孤立している島々には、そこでしか見られない不思議な動物や植物が生活している。キクの大木、海にもぐるトカゲ、飛ばなくなった鳥たち―。ガラパゴスと小笠原を中心に、ハワイ、カナリア諸島などの興味深い生態を紹介しながら、これらの動植物がどこからきたのか、どのように多様化したのかを考える。 第1章 進化論の島ガラパゴス 第2章 海洋島にカエルがいない 第3章 日本のガラパゴス小笠原 第4章 島は進化の実験場 第5章 大陸の中の孤島 第6章 島の生物が危ない メモ: |
|
ページのはじめに戻る
| 書名: ラムサ−ル条約 その歴史と発展 |
No.B520003 NDC519.800 |
| 著者・出版社: G.V.T.Matthews/釧路国際ウェットランドセンター |
|
| 内容: メモ: |
|
ページのはじめに戻る
| 書名: 野鳥の王国 湿地への招待 湖・沼・池・干潟の楽しみ方 |
No.B520004 NDC452.930 |
| 著者・出版社: タウンプランニング 環境庁野生生物研究会監修/ダイヤモンド社 |
|
| 内容: 湿地には多くの種類の生物が生息しています。適当なポイントに立てば、気軽に自然と親しみ野生の生物と触れ合う格好の機会を、湿地は提供してくれます。本書では日本にある代表的な湿地をとりあげ、それぞれの湿地と楽しみ方を紹介しました。読者の方々が、より楽しく湿地に親しめるようになることが本書の目的です。 メモ: |
|
ページのはじめに戻る
DUGONG
| 書名: ジュゴンの海と沖縄 基地の島が問い続けるもの |
No.B520013 NDC489.67 |
| 著者・出版社: ジュゴン保護キャンペーンセンター【編】宮城康博・目崎茂和・花輪伸一・大西正幸・浦島悦子【著】/高文研 |
初版2002/08/10 \1500 |
| 内容:
絶滅の危機にある“伝説の人魚”ジュゴンがすむ沖縄の海に計画された新軍事基地建設。21世紀、基地への依存から脱し、ジュゴンと共に生きるには、私たちは何をすべきなのか―。 第1章 ジャンの海―ある闘いの記録 ジュゴンと日本国憲法 沖縄 日本 世界 第2章 やんばるの海と山、そして人 第3章 北限のジュゴンを守るために 国連環境計画(UNEP)報告の意義と保護のための行動 国連環境計画(UNEP)のジュゴン保護のための調査報告書翻訳 第4章 ジュゴンの里に暮らす人々 |
 |
| メモ: ジュゴン保護キャンペーンセンター Save Dugong Campaign Center- SDCC -Official web siteのサイト紹介はこちら |
|
ページのはじめに戻る
| 書名: ジュゴンの嫁とり物語 |
No.B520009 NDC 480.400 |
| 著者・出版社: 中村幸昭/飛鳥新社 |
\1262 |
| 生きものたちに上等も下等もありません。人間が勝手に決めたのです。物言わぬ動物たち、その名誉を守るために私は動物の弁護人を買って出た次第です。 第1章 ジュゴンが鳥羽にやってきた 人魚のモデル、珍獣ジュゴンの人工保育はもう大変 ジュゴンを食べないで作戦 ほか 第2章 クジラが花見にやってきた エジプト政府 1頭10ドルの懸賞金でカバ狩りをさせ殺戮 ほか 第3章 動物たちは体内時計をもっている 第4章 小動物たちの「恋」と「愛」と出産 満月の夜の満潮時 世界一小さいクジラ・スナメリの出産で起こったのは 以下のメスは2本の足でオスを誘う タコのメスは愛の交歓中にオスの足を食いちぎる クロダイのオスは4歳でオスがメスになり卵を産む ほか 第5章 アホウドリはアホじゃない、バカ貝だってバカじゃない 第6章 鳥も魚もみんな人類の大先輩 人間とヤギを冒すエイズ そのウイルスの系列は同じである 北欧で金髪美人が減っているのは 酸性雨の仕業かもしれない ほか 終章 私が動物たちの弁護人になるまで―鳥羽水族館物語 |
 |
| メモ: |
|
ページのはじめに戻る
| 書名: 人魚の微熱 ジュゴンをめぐる愛とロマン |
No.B520010 NDC489.670 |
| 著者・出版社: 中村元/パロル舎 |
\1600 |
| ジュゴンが人魚!?ロマンを賭けた鳥羽水族館の記録。 1 ジュゴンは人魚なのか? ジュゴンを人魚と信じる人たち 人魚は実在するのか 何故、人魚には女性しかいないのか? ほか 2 ジュゴンって何者なの? 人魚だって息をする 海の牛たち ヒトと人魚との悲しい出会い 3 人魚の吐息 子孫を残すために 人魚のセックス? 男やもめに、欲望が湧く ジュンイチのダッチジュゴン 人魚のオナニー 乙女人魚の空ションベン ほか 4 人魚に愛された男たち 研究者たち 誰も知らなかったジュゴン ほか 5 人魚をめぐる冒険 危険が多い水族館の海外活動 セレナをめぐる冒険 ほか |
 |
| メモ: |
|
ページのはじめに戻る
| 書名: ジュゴン 人魚学への招待 |
No.B520011 NDC489.670 |
| 著者・出版社: 片岡照男/研成社 |
\2000 |
| 内容:
ジュゴンの棲む青い海と生活、広がる人魚への夢を語る。 1章 ジュゴンとはどんな動物―ジュゴンとその仲間たち 2章 ジュゴンの生活と生態―食性と行動 3章 ジュゴンの飼育と調査研究―パラワン島の海と空 4章 ジュゴンと人魚伝説 5章 世界のジュゴンとマナティーたち―調査紀行 6章 地球をひと廻り―海牛類の調査旅行 7章 ジュゴン保護のために―ジュゴンシンポジウムを終えて |
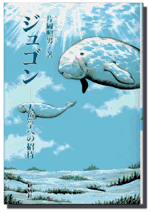 |
| メモ: |
|
ページのはじめに戻る
| 書名: ジュゴンの海は渡さない いのちをつなぐ美(ちゅ)ら海を子どもたちに |
No.B520012 |
| 著者・出版社: ジュゴン保護基金 編/ふきのとう書房 |
NDC319.800 \600 |
| 内容:
これだけは知っておきたい―ジュゴンの生態とあらたな基地問題。 日本最後のジュゴンを救え 沖縄のジュゴン等の保全勧告決議採択 ―世界自然保護会議(IUCN)総会報告 IUCN総会に向けたNGO、日米両政府のコメント IUCN総会におけるジュゴン等の保全勧告決議(全文) 知っておきたい―ジュゴンはどんな動物? 絶滅の危機!ジュゴン保護は待ったナシ ジュンおばぁとゴンおじぃのはなし |
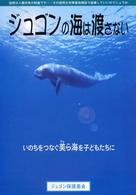 |
| メモ: ジュゴン保護基金委員会のサイト紹介はこちらから |
|
ページのはじめに戻る
| 書名: 未来へのノスタルジア ジュゴンの海へ |
No.B412049 NDC726.500 |
| 著者・出版社: 黒田征太郎/小学館 |
\1000 |
| 内容:
ジュゴンを守ることは地球を守ること。印税の一部がジュゴンを守る活動に使われます。 黒田征太郎[クロダセイタロウ] 画家・イラストレーター。1939年大阪に生まれる。現在、ニューヨーク在住。1969年に長友啓典と「K2」設立後、国内、海外でライブペインティング、壁画制作、ホスピタルアート等、幅広いアーティスト活動を続ける。 |
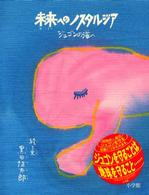 |
| メモ: |
|
ページのはじめに戻る