| �����F ���̏I��� ���ƌ��������V�̎��_ |
No. B149068 NDC 114.2 |
| ���ҁE�o�ŎЁF �咬��/�@�������� |
����2007/07/30 \1,890 |
| ���e�F ���͒N�ɂł��K���K���B�����̎����ǂ��}���邩�A�܂��g�߂Ȑl�̎����ǂ��e��邩�A������Љ�A�ǎ҂ɖ₢������B���ƌ����������Ƃ́A���܁i���j�����߂邱�Ƃł�����B 1 �w��R�ߍl�x���l���� ���A�ǂ��ŁA�ǂ̂悤�Ɏ��ʂ̂� 2 �U��ʂׂ��� ���y�Ɏ��� 3 ���ؓN�v �u��e�̎��v�Ƃ͉��� 4 �^�[�~�i���P�A���l���� �����ς����߂� 5 ��c�O�l��ӔN�̎����� ���Ԃ͉�A���� 6 �ݖ{�p�v�̎����� ���́u�ʂ�̂Ƃ��v 7 �u1000�̕��v�ɂ��� �S���Ȃ����l�͍� �咬���m�I�I�}�`�C�T�I�n �P�X�S�X�N���s���܂�B���s��w���w�����ƁB����w�@���w�����Ȕ��m�ے��C���i�ϗ��w��U�j�B���݁A�ޗǑ�w�����B |
|
| �����F |
|
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F �e���A�V���Ǝ��Ɣ߂��݂� |
No. B149067 NDC 114.2 |
| ���ҁE�o�ŎЁF �咬��/�@�������� |
����2002/08/30 \1,890 |
| ���e�F �ǂ�ȋ����ł��K���ɂȂ��B�������g�e���h���ƁB�����ɂł��邱�ƁA�ł��Ȃ����Ƃ���������B�ł��Ȃ����Ƃ�]�܂Ȃ��B�ł���͈͓��ŁA�őP��s�����B��������A�N�ɂ������Ȃ����炢�A��т�����K��������B �P�@�u���Ǝ��v�̌��� �Q�@�l�����ǂ������邩�\����x�O����̂��� �R�@�u�V����v�Ƃ������Ɓ\�u���Ɏ��v�͂���̂� �S�@�߂��݂�����\���c�M�j�̃O���[�t���[�N �T�@�u���̂��̑���v���l���� �U�@�e���\���́u���ւ̏�������v �咬���m�I�I�}�`�C�T�I�n �P�X�S�X�N���s���܂�B���s��w���w�����ƁB����w�@���w�����Ȕ��m�ے��C���i�ϗ��w��U�j�B���݁A�ޗǑ�w�����B |
|
| �����F |
|
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F �������g�E���� �k�V���Łl |
No. B149066 NDC 748 |
|
| ���ҁE�o�ŎЁF �����V��/���Z���^�[�o�ŋ� |
����1990/05/30 \1,274 |
|
| ���e�F �@�����ł͂Ȃ��A�N�w���ł͂Ȃ��A�Ȋw���ł͂Ȃ��B���������A�����ʂ�����O���̃����O�Z���[�B����1983�N2��12���A�V���ő�1��1990�N5��30���A��25��2007�N5��18���B ������Ƃ����̂��A�炪�Ȃ��ł���
�����i�˂ނ邵�܁j �ِS�i�܂Ԃ��̂���j ���ȁi���傤�̂����j �g���i�������Ƃ��j �V���i�Ă�̂����݁j �����ꂽ��R�[���� �����V��m�t�W�����V�����n �P�X�S�S�N�A���������܂�B�����|�p��w���G�Ȓ��ށB�C���h��U��o���ɃA�W�A�e�n�𗷂��A�w��x���Q�x�w�������Q�x�w�S���m�X���x�Ȃǂ��B��R��ؑ��ɕ��q�ʐ^�܁A��Q�R���|�p�܂Ȃǂ���܁B |
||
| �����F �ʐ^�� �����V��I�t�B�V�����T�C�g�@-fujiwara shinya official site- �͂����炩��BMemento mori�̍�i�̈ꕔ���T�C�g��Ō����܂��B |
||
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F �Ȃɂ����Ȃ�������킹�� |
No. B149065 NDC 914.6 |
| ���ҁE�o�ŎЁF �����V��/�������� |
����2003/08/13 \1,890 |
| ���e�F ���e�����E���邽�тɎl�����������B����Ȓ��҂��s��ȌZ�̍Ŋ��ɗ�����A�g���S������ĖK�ꂽ�O�x�ڂ̎l���ւ̗��́c�B���̋����ɗ��n����F�ɌZ�̊炪�d�Ȃ�A�O�\�Z�ԎD���̐����ŋF��c���̎p�Ɂu���S�v�̋��n���݂�B������҂̎����ǂ�����邩�A�����ɋF��̂��B�������L�����l������n�}�t���B ��{ ���� �V���� �Ȃɂ����Ȃ�������킹�� ���炩�Ȃ� �Â����v ���e �F�H���� ���� �̉ԓd�� �l���̃I�E���S�[�� ���Ɋ� �t�̔L �܂Ȃ����̐��t �x�m�������l ������ �������� �n ���� ���̋Z�@ �c�݂̉� �t�ԍl �����V��m�t�W�����V�����n �P�X�S�S�N�A���������܂�B�����|�p��w����Ȓ��ށB��R��ؑ��ɕ��q�܁A��Q�R���|�p�܂Ȃǂ���܁B |
|
| �����F ���t���Ɂi2006-10-10�o�� \829�j���� |
|
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F �����V�����N�� �u���v���q�ǂ��ɋ����� |
No. B149054 NDC 375 |
| ���ҁE�o�ŎЁF �F�s�{���q/�������_�V�� |
����2005/10/10 \756 |
| ���e�F �u�l���E���Ă݂��������v�Ǝq�ǂ����E�l��Ƃ�����B���̑�����`���邽�߂ɁA�����͉����ł���̂��H���{�ł̕��y���]�܂��u�f�X�E�G�f���P�[�V�����v�̎��H�Ⴉ��l����B �P�́@���߂�ׂ����� ���ʂ̎q�ǂ����� ���鋳�t�̒��� �Ώۑr���̗��� �菇�ƕ��@ �����������ւ̊K�i ���k�̐� �Q�́@�ω��ւ̓��� �b�̐l �A���t�H���X�E�f�[�P���̑��� ������h�����߂� �܂̒�� �u�������v�ւ̊�] ���鏗���̎��G�ߒQ�̃v���Z�X �V�㐢��̃f�X�E�G�f���P�[�V���� ����F�߂�E�C �R�́@���H������ �Ċ��Z�~�i�[ ���ȉ� ����ɗ����t ���C��̌ߌ� �w���� �z�X�s�X����̔��M �u���ʁv����̒E�p �S�́@���ւ̌����� �����̉̐� �̌����ߌ� �v���̋��L ���ꂼ��̕��ی� �܂̗��R ���k�Ƃ̉��x�� ��Z�N���o�� �F�s�{���q�m�E�c�m�~���i�I�R�n ��ÁA�l���A�����A�X�|�[�c�ȂǂɊւ���m���t�B�N�V������G�b�Z�C���A�V���⌎�����ɔ��\ |
|
| �����F |
|
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F �����l�V�� ���ɂ䂭�l�̂��߂̈�� |
No. B149053 NDC 490.15 |
| ���ҁE�o�ŎЁF �X�����F/���{�����o�ŋ��� |
����2003/11/10 \693 |
| ���e�F �]���A���E�A���y���A�������B���܂��͗Վ����}�����l�����ɁA�Í������̈�w��@���͂ǂ����������Ă������B�q���̂��r�̏I�����ǂ��������Ă������B��������}���鎀�́A�����I�ȗl����T��A���ɗՂސl�тƂ̎��Ȍ��茠��Ƒ��̈ӎv�A��t�E��ÊW�҂̔��f��i�@���߂ȂǁA�܂��܂����G��������̂Ȃ��łQ�P���I�́u���ɕ��v���l�@����B ��P�́@�V�������̊T�O�\�]�� ��Q�́@���̂��܂��܂ȗl�� ��R�́@�l�͎��疽���k�߂Ă悢�� ��S�́@�I�����̈�Á\���y�����瑸������ ��T�́@�^�[�~�i���P�A ��U�́@���y���̗e�F ��V�́@���ɂ䂭�l���߂�����_ �X�����F�m�����I�J���X�q�R�n ���{�ԏ\���Ј�ÃZ���^�[���_�@���B������w���_�����B�P�X�R�O�N�����s���܂�B������w��w�����ƁB�{������p�|��֓��J�Еa�@�������C���Č��E |
|
| �����F |
|
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F �����V�� ������̍�@ ���ւ̍\���A���ւ̍\�� |
No. B149050 NDC 914.6 |
| ���ҁE�o�ŎЁF �R�ܓN�Y/�������_�V�� |
����2002/09/25 \714 |
| ���e�F �����낪��܂�Ȃ��\�B���������v��������Ȃ���A�킽�������͓��X�𑗂��Ă���B���{�l�̂�����ɐ����������Ă���̂ł͂Ȃ����B���҂Ƌ�������́B�l�Ԃ̔w��ɉB����Ă���g�������h���邢�́g�������h�ւ̊��B���ɑ���ԓx�B��܂�ʂ����낪������s�m���Ȃ��̂Ƃ��Ă���B�{���́A���N���{�l�̂���������ߎv�������点�Ă������҂ɂ��A�h�邬�Ȃ�������������߂̃��b�X���Ȃ̂ł���B ��P�́@������̌����i ��Q�́@�u���v�̗� ��R�́@�l�ԁA���̖��m�Ȃ���� ��S�́@���̎��̍�@ ��T�́@���_���ɂ��� ��U�́@�`���̂�����A�ߑ�̂����� ��V�́@�፷���̋L�� �R�ܓN�Y�m���}�I���e�c�I�n �P�X�R�P�N�i���a�U�N�j�A�T���t�����V�X�R�Ő��܂��B���k��w���ƁB�������j���������ً����A���P���q�Z����w�w���Ȃǂ��o�āA���݁A���ۓ��{���������Z���^�[���� |
|
| �����F |
|
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F ���t�V�� �o��Ƃ��Ă̎����w |
No. B149049 NDC 114.2 |
| ���ҁE�o�ŎЁF ��g�h��/���|�t�H |
����2004/05/20 \735 |
| ���e�F �Ȃ��l���E���Ă͂����Ȃ��̂��\�B���̖₢�ɏ\�S�ɓ�������l�͂ǂꂾ�����邾�낤�B�����̐g�̂�͎̂���̎��R���B���āA�ǂ����܂����B�������A���y�������Ȃ��͖]�݂܂����B���������A�ϗ����ϗe����Ȃ��A���l�̉��l�ςɑ���ꂸ�A�����Ȃ��邵�A�[�����Ď��ʂ��߂Ɏ���̎����ς̊m�����B�C�s�̕a���w�҂��J����h���I�ȃq���g�̐��X�B�����ǂ��萶���������ł��B ��P�́@���l�̉��l�ςɑ����Ȃ����߂� �������E���y���Ƃ͉��� ����ڐA�͗��z�I�Ȉ�Â��@�ق� ��Q�́@�l���E�����߂̃��[�� �Ȃ��l���E���Ă͂����Ȃ��̂� ���Y���x�͔p�~���ׂ����@�ق� ��R�́@���Ǝ��̌����I���p ���E�͋������̂� �g�̂�͎̂����̏��肩�@�ق� ��S�́@�����̎����ς������߂� �ϗ��E�����͂ǂ����ĕώ�����̂� ���R�E�ɂ�����l�Ԃ̈ʒu�@�ق� ��g�h��m�i���o�R�E�W�n �P�X�S�P�N�A�L���s���܂�B�L����w��w�����B�V�Q�N�A�����ϕa�@�Տ��a���Ȉ㒷�B�V�S�`�V�U�N�A�č����������a�����ɗ��w�B���������p��̌����ɏ]���B�W�O�N�A���������p��ە��ނ̍���v��ɎQ���B�W�Q�N�A�L����w�����Ȋw�������A���݂ɂ�����B��啪��͌��t�a���w�A�����ϗ��B�X�V�N����A�L���s�̎�����������������̗��R�ɕ邷 |
|
| �����F |
|
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F �u�k�Ѓv���X�A���t�@�V�� �����u����̐��E�v���� �����������Ĕ��������� |
No. B149048 NDC 181.4 |
| ���ҁE�o�ŎЁF �Ђ낳����/�u�k�� |
����2002/07/20 \819 |
| ���e�F �V�����a�C�������A�Ɋy��y�ւ̓��B��������B�Ɋy�ւ͒N�ł��s����̂��B������C�E���������ł��n���ɑ���̂��B���r�̐�̘Z�����E���ЂƂ߂��肵�A�����ւ̊�]�����Ă���������ƁA�����̐�����������B ��P�́@���ւ̗����� ��Q�́@�����ւ̗����� ��R�́@�n���߂��� ��S�́@��S�ƒ{���̐��E ��T�́@�V�E�ƏC���ƛO�k ��U�́@�Ɋy�߂��� �Ђ낳����m�q���T�`���n �P�X�R�U�N�A���ɐ��܂��B������w��w�@�l���Ȋw�����Ȉ�x�N�w��U���m�ے����C���B�C�ۑ�w�Z�������o�āA�@��������������ݗ��B�܂�̉��B�@���]�_�ƁB�@�������ʎ�����A�a��ꂪ���ȓ��{�ɂ����āA������g�߂Ȃ��̂ɍL�߂�[�֊����𑱂��� |
|
| �����F |
|
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F ��g�V�� ��x�ڂ̑剝�� |
No. B149047 NDC 914.6 |
| ���ҁE�o�ŎЁF �i�Z��/��g���X |
����1995/10/20 \714 |
| ���e�F �u�l�Ԃ͕a�C�Ŏ��ʂ�Ȃ��B�����Ŏ��ʂ�v�u������Ă����тꂿ�Ⴂ���܂���B�����т�Ȃ��悤�ɂ����Ȃ���v�\������m�b�ɖ����������̌��t�̐��X�A�����āA�u��l�Βk�v��u���h�L�������g�ō\�����鎆��o���G�e�B�B�v�킸���A�₪�Ă���݂�l����������B�w�剝���x��S���ǎ҂ɂ�����Җ]�̑��e�B �P�@�����\�u�����т�Ȃ��悤�ɂ����Ȃ���v �Q�@�a�C�\�u�l�Ԃ͎����Ŏ��ʂ�v �R�@���\�u�U����c������U����v �S �@���\�u���肪�������Ƃ݂͂�Ȃ����������v �i�Z��m�G�C���N�X�P�n �P�X�R�R�N�A�����E�̏�y�^�@�Z�E�̎��j�Ƃ��Đ��܂��B����c��w�݊w���������̐��E�ɓ���A������ƂƂ��ē��p������킷�B�Ȍ�A���W�I��e���r�̍\�����肪�������A�i��ҁA�쎌�ƁA����ȂǕ��L���W�������Ŋ����� |
|
| �����F |
|
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F ���ȂȂ��ł��闝�R |
No. B149046 NDC 104 |
| ���ҁE�o�ŎЁF �h�c����/���w�� |
����2004/05/10 \1,785 |
| ���e�F �����邱�Ƃ̈Ӗ��A�V���邱�Ƃ̈Ӗ��A�����������ɂ��邱�Ƃ̈Ӗ��B����l�́u���̂��v�̍������̎コ�A�₵���A���₷���̗��R��s�s������������������B�s�s��t�@�b�V�����Ȃǂ̕]�_���當�w�_�܂ŐV���E�G���Ȃǂŕ��L�������𑱂��Ă���N�w�҂̌��㕶����]�ł���B����l�̓����ł���u���̂��v�̍������̎コ�A�₵���A���₷���̗��R��s�s�����̒�����l����B�{���̓��e��4���\���ł���B��1���u���ɓN�w�I�Ȏ���v�́A���{�͐����E�o�ρE����Ȃǂ��������Ă��鍡�����A�l����Ƃ����N�w�I�v�l���K�v�ł���ƁA���j�I�ɘ_����B��2���u�₵������v�́A�s�K�̐����肪�������A�Ȃ��K���_������Ȃ����ɂ��āA���w��i�Ȃǂ����p���Ȃ���R�~���j�P�[�V�������Ƃ�����̎₵��������𖾂���B��3���u�ЂƂƂЂƂ̂������v�́A��Â⋳�猻��ł̂ЂƂƂЂƂ̞B���ȊW�A�ω�����Ƒ��̂������ɂ��Č��y����B��4���u�s�s�I�Ȋ���v�́A�s�s�̕������Ƃ��āA�l�X�ȕ����̏W�Ϗ��ł���s�s�ƂЂƂƂ̊W�A���{�ɂ����Ẵu�����h�̈Ӗ������B �P�@�₵������ ��������䂭�A����������\����̊�ȑr������ɂ��� ���ȂȂ��ł��闝�R�\�������K���_ �Q�@�ЂƂƂЂƂƂ̂����� �����Ȃ����\��Â̌���� ���낢�䂭���n�̃C���[�W�\����̌���Ł@�ق� �R�@�s�s�̊��� �s�s�̃e�N�X�`���A �u��v�Ƃ������ہ\����G���`���������́@�ق� �S�@�N�w�ƃt�@�b�V���� ���ɓN�w�I�Ȏ��� �u�����h�ɉf��j�b�|�� �h�c����m���V�_�L���J�Y�n �P�X�S�X�N���s�s���܂�B���s��w���w�����ƁA����w�@���w�����Ȕ��m�ے��C���B����w���w�������Ȃǂ��o�āA���݁A����w��w�@���w�����ȋ����B�N�w�E�ϗ��w��U�B |
|
| �����F |
|
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F �����܃v���}�|�V�� ����ǂ��Ȃ�́H |
No. B149043 NDC 114.2 |
| ���ҁE�o�ŎЁF ���Џ@�v/�}�����[ |
����2005/01/25 \756 |
| ���e�F �|���������̂��� ���� ���Ƃ͉��� ���̒�` �u����͉́v�̎��̐��E ���ʂƂǂ��֍s�� �ق� ���� �u���̐��v���āA�ǂ������Ƃ���H �u���̐��v�Ƃ����Ăѕ� ���~�Ƃ������� ���E�Ƃ��Ă̎R �Ɋy�Ƃ����ِ��E �Վ��̌����������� �ґz�Ɓu���̐��v �C�̂��Ȃ��Ɋ҂� �n���ƋɊy �Ín�Ƃ���� �ق� ��O�� �����āA����̂��ȁH �m���ƉȊw�̌��E ���Ɨ�̈Ⴂ �u��v�ɂ��� ���܂��܂ȗ։� �S�ƈӎ��Ɨ�ƍ� �ق� ��l�� ���炽�߂Ď��Ƃ͉��� �������ΓI�H ����̂Ȃ��̐��� ���܂꒼�� �U������݂� �Ӓ��̖� �ق� ���Џ@�v�m�Q�����E�\�E�L���E�n �P�X�T�U�i���a�R�P�j�N���������܂�B��ƁB�V������哹��ł̏C�s���o�āA���݂́A�ՍϏ@���S���h���ڎ����Z�E�B�c���`�m��w���w���������w�ȑ��ƁB�����Ɂw���A�̉ԁx�i��S��\�܉�H��܁j�Ȃ� |
|
| �����F |
|
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F �m�b�̐X���� �F���Â� |
No.B149040 NDC 914.6 |
| ���ҁE�o�ŎЁF �������� ��/������ |
����2004/12/15 \650 |
| ���e�F ��[�N���A���c�M�q�A�O���R�I�v�A�J�����A�r�g�����Y�A�F�앐��A��ˎ����A�h��Y�A�����A�Ό��T���Y�A����Ђ�c�������D�B�����l�̎��ɍۂ��āA���̗F�����������ɁE�^���E�lj��E��]�̌��t�̐��X�B���ɂ��ēƎ��̌������������Ҏ҂��I�肷�������A��ʂ̒Ǔ����W�B���ɔœ��ʕ҂Ƃ��ĕҎ҂ւ̒�����V���Ɏ��^�B �P�@���� �֓��g�i���a�Q�W�N�Q���Q�T���v�j�\��łɂ��Đꉡ�i�k�m�v�j �������i���a�R�O�N�Q���P�V���v�j�\�������̎��i�h��Y�j �~��t���i���a�S�O�N�V���P�X���v�j�\�悫��y�~�莁�i��������j ����M�O-�Í����u�� ��[�N�� -������ ������ -�����o�C ���c�M�q -�H�R�����q ���яG�Y -�����o�C �L�g���a�q -�˔N�� �Ėډ�q -�a�c�� ���@�O -�F�앐�� �Ό��T���Y -�Ό��T���Y �剪���� -����� ��ˎ��� -������ �F�앐�� -����N�� �J���� -�O�Y�N�Y �r�g�����Y-�i�n�ɑ��Y ��ԍG -�؉����� �@�ق� �Q�@�Ǔ� �J�菁��Y�i���a�S�O�N�V���R�O���v�j �\�J�蒩����̏I���i�O���R�I�v�j �O���R�I�v�i���a�S�T�N�P�P���Q�T���v�j�\�O���R�I�v���̎��̂̂��Ɂi���c�~�j �u�꒼�Ɓi���a�S�U�N�P�O���Q�P���v�j �\�I���̋L�i����O�V�j �~�n���q -���˓��⒮ ����Ђ� -���Ђ��� ���� -��]���O�Y �R�@���� ��������i���a�Q�Q�N�P�Q���R�O���v�j�\�����i��[�N���j ���R�G�V�i���a�T�O�N�T���P�P���v�j�\�����i�g�s�~�V��j �h��Y�i���a�T�P�N�P���Q���v�j�\�����i�����Y�j �M������ -�O�H���Y �A���r�� -�ےJ�ˈ� �H���C�u -�����^��Y �ΐ�~ -�������[ ���ɔœ��ʕ� ��������i����8�N9��29���v�j �\���� �����͑��Y ��� ���R���O�Y ��������m�G���h�E�V���E�T�N�n �P�X�Q�R�i�吳�P�Q�j�N�R���Q�V���A�������܂�B���B��A�A�_�˂Ɠn��A�P�P�̂Ƃ��ɃJ�g���b�N�̐������B�c���`�m��w���w�������ȑ��B�P�X�X�U�N�X���Q�X������ |
|
| �����F �F���Â� ISBN:433405188 ������ (1991-09-30�o��) NDC����:914.6 :\1,223�̕��ɉ� |
|
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F �����ܕ��� �����邩�Ȃ��� |
No. B149038 NDC 914.600 |
| ����/�o�ŎЁF �R�c����y�ҁz/�}�����[ |
����1995/01/24 \525 |
| ���e�F
�l�͒N�ł��S�̒�ɁA���܂��܂Ȃ��Ȃ��݂�����Ȃ��琶���Ă���B�a��V�������łȂ��A�ق�̏����Ȃ��Ƃ�A���ɂ͈����邪���߂̂��Ȃ���������B���A��Ȃ��Ƃ́u�����邩�Ȃ����v�ɖڂ������A�l�Ԃ̂͂��Ȃ��A���͂�m�邱�Ƃł͂Ȃ����낤���B�u�����邩�Ȃ��݁v�Ɛ^���ɒ��ʂ��A�l���̕��ƌ��݂𑝂�����l�B�̏�����ǂށB�����V���u�V���l��v2003�N4��5���ŏЉ�B �f�O����Ƃ������Ɓ@�@�i�R�c����j �@�� ���钩�́@�@�i�g��O�j �@ �� �o������߂�E�Ō�̏C�Ɓ@�@�i�������q�j �߂��˂̔߂��݁@�@�i�~�n���q�j ���̃A���h���@�@�i�����V�q�j �@ �� �Z�̃g�����N�@�@�i�{�Z�j ��x�Ɛl�Ԃɐ��܂ꂽ���Ȃ��@�@�i�F��M�v�j ���Ɏ��\�܍߂̊����@�@�i�ܖ��N�S�j �@ �� �R�̐l���@�@�i���c���j�j �w��߂�ꂽ���L�x����@�@�i�A���h���W�b�h�j �w�f��������x����@�@�i�i��ו��j �@ �� ��̔߂��݁@�@�i���R���ہj �]���ƊC�@�@�i�Ό��g�Y�j �@�� ��ڂɌ����ā@�@�i�����O�X�g���E�q���[�Y�F�哇�n��j ����ꂽ���̒��N�����߂ā@�@�i���j���j �@ �� �e�q���J�ɂ��Ă̒f�z�@�@�i����ׁj |
|
| �����F |
|
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F ��g�V�� ���Ǝ��̐S�͗l |
No. B149037 NDC 490.150 |
| ����/�o�ŎЁF �匴���m�Y/��g���X |
����1991/03/20 \672 |
| ���e�F
�����ẤA�a�C��f�Đl�Ԃ�f�Ȃ��Ƃ�����B�]���A����ڐA�A���m�A�^�[�~�i���E�P�A�ȂǁA���҂����܂����͋ߔN�傫���ς��A�l�̐S���������_�Ȉ�̖������܂��܂��傫���Ȃ��Ă��Ă���B�S�a�߂錻��l�▖�����҂ȂǁA�Տ��̌���Ŋ��҂̐����A���Ƃ͉����A���Ƃ͂Ȃɂ��A��Â̖����Ƃ͉������l����B �͂����� �P�@���Ɛ��_��� �Q�@����l�̐S�̕��i�T�@�@�v�t���nj�Q �@ �@���H�� �@ �@�V���i�[���z�����N���� �@ �@�o�Z���� �R�@����l�̐S�̕��i�U�@�@�s�N���̊�@ �@ �@�A���R�[���ˑ��� �@�@ �o�Ћ��ۂƂ��a �@�@ ���a�Ɛ_�o�� �S�@���E�҂Ƃ̑Θb �@�@���E��}�҂̎�X�� �@�@���E�҂Ƃ̑Θb �@�@���ʂقǏ����肽�� �@�@�����҂����̂��̌� �T�@�����Âɂ���S �@�@����̍��m�ƐS�̊��� �@�@���̒�`���čl���� �@�@���������l�����l �@�@�^�[�~�i���E�P�A���߂����� �U�@������~�] �@ �@�X�c�Ö@�Ɛ��̗~�] �@ �@�i���̐��� �@ �@�����Âɂ����鐸�_�Ö@ ������ �匴���m�Y�@�m�I�I�n���P���V���E�n �P�X�R�O�N�A���m���ɐ��܂��B�������b���ȑ�w�𑲋ƁB�������b���ȑ�w���������o�ĕl����ȑ�w�����ƂȂ�A�P�X�X�U�N�ɓ���w���_�����ƂȂ�B |
|
| �����F |
|
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F ���t�V�� ���܂悤������ �@���̗� |
No. B149036 NDC 160.400 |
| ����/�o�ŎЁF �v�ۓc�W�O/���|�t�H |
����2004/03/20 \735 |
| ���e�F
���̂��̊�@�̎���ł���B���������̌���Ɍ���Ȃ��B��@�͎������̓���ɂ���B�H�������A��Â�C���t������������A����Y�ꂽ���̂悤�ȕ����̑����ɁA�s�����s�C���Ȗe���̂�������B�����ς��h��Ă���B�i�N�A���{�͂��߃A�W�A�A���B�A���ߓ��̑��l�ȏ@���������ۂɕ��ݐl�X�̐������ɂւ̎v���g�ŒT���Ă����@���w�҂��A��̕a�ςƂ��̎��Ɍ��������A���߂Ė₤�\�l�ԂƂ͉����A�l�͎����ǂ������̂��A���܁A�@���͂ǂ�ȗ͂�^������̂��c�B �͂��߂Ɂ@�����̉��ŘV�l�ɏo� ��P�́@�g���܁h�Ƃ������� �@ �L�����ƕs�� �@ �����Ăт�������́@�@�ق� ��Q�́@�B���Ȑ��Ǝ� �@�a���Ɖ����͂��� �@�]���Ƒ���ڐA�@�@�ق� ��R�́@���_���͐��Ǝ����ǂ��Ƃ炦���� �@�����@���ςƁu���̐��v �@�s�E���Ƃ��������ρ@�W���C�i���̌������o �@�A�j�~�Y���@�����Ƃ����s�𗝁@�@�ق� ��S�́@�B��_�����E�ɂ����鎀�Ɛ� �@���_�����̌�����` �@�u�_�̓���v�Ɓu�_�̊�v �@���y���Ƃ������ɕ��A�������@�@�ق� ��T�́@�C���h�E�x�i���X�̊ݕӂ� �@�u����҂l�̉Ɓv �@���҂̟��� �@�։�Ƃ��������ρ@�@�ق� ��U�́@���{�l�̐��Ǝ��ւ̎v�� �@�썰�ւ̋���Ɛe���� �@��y�Ƃ���������� �@���Ǝ��̎��R�� �@�NJ��@�@���ɂ䂾�˂Đ����� �I�́@�����玀�ցA�����琶�� �@�i���̒��̑މ� �@�u���������v���邢�́u���ɂ����v �@�n���Ɍ������� �@�`�������W�ƒ��O�@�@�ق� �v�ۓc�W�O �m�N�{�^�m�u�q���n �P�X�S�P�N�A��������B����c��w���ƁB�����E���m�N�w���w�сA�̂��ɃA�W�A�e�n���璆�ߓ��A���[���b�p�ɒ������d�ˁA���_���E��_����l�X�̃e�[�}�Ŕ�r�����B���݁A��w�A�e�n�̃Z�~�i�[�A�J���`���[�X�N�[���Ŕ�r�@���E�����ς��e�[�}�ɍu�������� |
|
| �����F |
|
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F ���̉Ȋw�A���̓N�w �{�V�Ўi�Βk�W |
No. B149033 NDC 914.600 |
| ����/�o�ŎЁF �{�V�Ўi/�����o�� |
����2004/07/22 \1470 |
| ���e�F
�l�Ԃ̐g�̂ƈӎ���O���U�B �T �����с\�����Ǝ��R�̕s�v�c�Șb �����^�\��U�w�ƍl�Êw �������q�\�~�~�Y�̂���L���� ���C�т������\�����̊��o�Ƃ������R �����͓��\�L���A�����A�A�ȂƑ����Ă䂭���� �M�z�j�\�g�̂��߂����ۂƒ��� �U �b��P�I�\�Õ��p�����g�̂̉\�� �g���쎡�\�W�߂āA���ׂāA�l���邨�����낳�@���� ��������\���̂Ǝ��́A�ǂ��炪�|���H �������\���Ǝ��ւ̏���� �D�g���v�\���Ȉӎ���ɏグ�� ���R���J�\�X�s���`���A���ƃ}�e���A�� ������F�\�Ђ�߂��͉����ƂƂ��ɂ���Ă��� �V ���Ƃ����������\���̍��o�A�����̍��o �r�c���F�\��\�ꐢ�I�̑�ӂƏz�� �r�c���q�\�g�̂��g���čl�������� �Ėږ[�V��\�}���K�̕��@���g�]�h�œǂ݉��� ��ĉ��\�J���̎��� ��������\������N�w�Ƃ̏o� �{�V�Ўi �m���E���E�^�P�V�n �P�X�R�V�N�_�ސ쌧���q�s���܂�B������w��w�����ƌ�A�C���^�[�����o�ĉ�U�w�����ɓ���A������w��w�@��w�n�����Ȋ�b��w��U���m�ے��C���B�W�{���ȂǁA�����̂������A���w�I�̈�ł������̏���L���Ă����B�P�X�X�T�N�ɓ�����w��w��������ފ��A�P�X�X�U�N���k����w�����B������w���_���� |
|
| �����F ��,�}���K,��U�w |
|
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F �V���V�� ���̕� |
No. B149032 NDC 914.600 |
| ����/�o�ŎЁF �{�V�Ўi/�V���� |
����2004/04/15 \714 |
| ���e�F
�o�J��荂���ǂ��������E�E�E�E�E�B�������A�|�ꂸ�A�l�����ŏI�B�������͎����������߂��Ă͂��Ȃ����낤���B�����Ȃ��ӂ�����Ă͂��Ȃ����낤���B�����l����A���̒��������Ă���B�����������Ă���B���̐l���̋L���͕��e�̎�����n�܂��Ă��܂��B�l���͕��S��������n�܂�Ƃ���ƁA���̏ꍇ�ɂ͐l�����ŏ����玀�ɐڂ��Ă������ƂɂȂ�܂��B����Ŏ��Ƃ��������悭�����̂�������܂���B��U�w���U�������R�̈���A�����ɂ���̂�������Ȃ��B�����v�����Ƃ�����܂��B���܂ł͑����̐l���A�����l�������Ȃ��Ǝv���Ă���悤�ł��B�ł����܂ɂ����������Ƃ��l���Ă����ƁA�������S���Đ������邩������܂���B�Ƃ��������͈��S���Đ����Ă��܂�����ˁB�i���Ƃ������j ���́@�w�o�J�̕ǁx�̌������� �@�@�l���̍ŏI�� �@�@�l�����ȂȂ��c�n�@�@�ق� ���́@�Ȃ��l���E���Ă͂����Ȃ��̂� �@�@�����̗L�l�F���D�͉����� �@�@�u�[�^���̂��ꂳ�� �@�@��x�ƍ��Ȃ����� �@�@�l�Ԓ��S��`�̊낤���@�@�ق� ���́@�s���̕a �@�@�s���g�̐l �@�@�u�{���̎����v�͖��G�̘_ �@�@���ƃE���R �@�@���̓s�s�M���V�� �@�@��Ԏ�̕|���@�@�ق� ��O�́@�����̋��� �@�@�f�f���͖��W �@�@�N�G���_��H �@�@���N�́u���v�͕ʐl �@�@�����Ă��鍜�@�@�ق� ��l�́@���̂̐l�� �@�@��l�̂̎��� �@�@��l�̂̎��� �@�@�O�l�̂̎��́@�@�ق� �@�@ ��́@���̂͒��Ԃ͂��� �@�@���߂̉��̈Ӗ� �@�@�Ȃ������͕K�v�� �@�@�l��l�Ƃ͉��҂� �@�@ �u�Ԉ����v�͓���R�� �@�@ �x�g�����h�N������{�ɂ��Ȃ����R�@�@�ق� ��Z�́@�]���Ƒ����� �@ �@�C�����l�̉Α� �@�@ ���Y�Ƃ��������� �@�@ ����ڐA�̕s�v�c �@�@ �P�l�f�B�͗������w�@�@�ق� �掵�́@�e���E�푈�E��w���� �@ �@�푈�ƌ�����` �@ �@���`�̉����t�����܂��� �@ �@�푈�Ől���炵 �@ �@�R����`�҂͐푈��m��Ȃ� �@�@ ���v�Ƃ͉����@�@�ق� �攪�́@���y���ƃG���[�g �@�@���y���͋ꂵ�� �@�@�G���[�g�͉��Q�� �@�@�Y�k�̔w�����d�� �@�@��U�����̉ԁ@�@�ق� ���́@���Ɛl���ٓ� �@�@���̋��|�͑��݂��Ȃ� �@�@�V�X�Ƃ͉��� �@�@���̌��p �@�@�����c�������̂̉ۑ� �@�@���X�s�\�@�@�ق� �{�V�Ўi�m���E���E�^�P�V�n �P�X�R�V�N�_�ސ쌧���q�s���܂�B������w��w�����ƌ�A�C���^�[�����o�ĉ�U�w�����ɓ���A������w��w�@��w�n�����Ȋ�b��w��U���m�ے��C���B�W�{���ȂǁA�����̂������A���w�I�̈�ł������̏���L���Ă����B�P�X�X�T�N�ɓ�����w��w��������ފ��A�P�X�X�U�N���k����w�����B������w���_���� |
|
| �����F ���y��,�]�� |
|
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F �����̋F�� ��������ɂ݂�l���ρE������ |
No. B149031 NDC 913.360 |
| ����/�o�ŎЁF �Ζ쏉�}/�ɓV�� |
����2003/1/20 \1050 |
| ���e�F
�������Ə��������Ƃ̉₩�ȗ�����Ƃ��������łȂ��A��l��l�̏����̐�����Y�݂�ꂵ�݂��[��������Ă��邵�A�Ⴍ���ďo�Ƃ��Ă䂭�l������̂ŁA�y���C�����ł͓ǂ߂Ȃ��Ȃ����B�e���ɂ͂��낢��Ȑ_�A���A�o�T�A�M�S�ɐM����l�X�̐����������Ă���B�������Ⴂ�̂ɕ����ɏڂ����A�S���Ȃ����l�ɑ��Č�̌䋟�{�J�ɍs���̂��ӊO�ł������\�u��������v�ɓo�ꂷ�镧�����͂��߁A�_����A�z���Ɏ���܂ł̏@���V���T���o���A�����̐l�тƂƍ�Ҏ������̏@���ρE�l���ς͂������B ��P�́@�e���ɏ����Ă���@�� ��Q�́@�e�@�h�̌�{�� �@����ɕ� �@�߉ޖ��� �@��t�� �@��ḎՓߕ� �@����@�� ��R�́@�������ƌO�̐��i �@�������̕� �@�O�̐��i ��S�́@�،��o�i���@�E�i�j�ƌ������� �@�P�����q�̗��P�`�U ��T�́@�������Ə��������̐M�S �@�������Ə@�� �@���̏�Ɩ@�،o �@���̏�ƏZ�g���_ �@��顂ƒ��J�ω� ��U�́@��҂̕����� ��V�́@��������̕����v�z |
|
| �����F ���A��������,�،��o,�@�،o |
|
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F ���̂��A�����Ȃ��� ���Ȃ��͐l���̍Ŋ����ǂ��Ō}���܂��� |
No. B149028 NDC 494.500 |
| ����/�o�ŎЁF �ʒn�C�q/�W�p�� |
����2003/11/30 \1600 |
| ���e�F
���҂���́A�Z���Ă��c��̂��̂����Ȃ������߂ɉƂɋA��܂��B���ɂ䂭�l�ƌ��������A���ɋꂵ�݁A�����ď����Ƒ��́A�܂����łȂ��A��������̊��𗬂������ƂŁA�߂��݂����u�ƂŊŎ�邱�Ƃ��ł����I�v�u�悭�����܂Ŋ撣�ꂽ�I�v�Ƃ����B������������ƌ����܂��B�Ƒ��͔[���̂������Ŏ��̌�A���҂��傫�ȑ��蕨���₵�Ă��������ƂɋC�Â��܂��B�u��ɐ�����v�Ƃ������Ƃł��B�����ĉƑ����A�����Ȃ������Ƃ��ł���̂ł��B �ŏ��̕���@�@���ɂ͌��肪���� �P�̏́@���Ȃ��͐l���̍Ŋ����ǂ��Ō}���܂��� �Q�̏́@���A�K���T���̗��̂����ł� �R�̏́@�܂����ɂ����Ȃ��A�����Ɛ��������I �S�̏́@�a���e�ꂽ�Ƃ��납�琶���Ȃ��� �T�̏́@���ɏꏊ�̑I�� �U�̏́@���̂��͒N�̂��̂ł��� �V�̏́@���ʂ��Ƃ͕����邱�Ƃł͂Ȃ� �W�̏́@�\���̐N�Ɏc���ꂽ�Ō�̓��X �X�̏́@�D���Ȃ��Ƃɒ��킵�āA�]�����P������ 10�̏́@���e�̎����ǂ����z���邩 11�̏́@�Ƒ�������������āA���邪�܂܂����l�J�� 12�̏́@�ݑ��Â�I������Ƃ������� 13�̏́@���̎d���ɏo��āA���͍K���ł� �Ō�̕���\���ɂ䂭�l�̐[���S���u���Ɋ��Y���� �ʒn�C�q�m�^�}�`�q�f�R�n �P�X�S�S�N�A�F�s�{�s�ɐ��܂��B���É��s����w��w�����ƌ�A���_�Ȉ�Ƃ��Đ��_�a�@�ɋΖ��B�P�X�V�Q�N�A�G���U�x�X�E�L���[�u���[�E���X�i�A�����J�̐��_�Ȃ̏���j���A���҂ɃC���^�r���[�����Ă܂Ƃ߂��w���ʏu�ԁx�i�������Ɂj��ǂ��Ƃ��A���҂̏I����Âɂ�������邫�������ɂȂ�B�_�ސ쌧���؎s�Ƀz�X�s�X����邽�߂̎s���^���ɂ������A�P�X�X�Q�N�ɉ��l�S���a�@�z�X�s�X�a�����ɏA�C�B���̌�A���؎s�ɖ������҂̏Z���Â��x������u��߃N���j�b�N�v���J�݁A�Q�O�O�R�N�P�O�����݂P�S�O�l�̊��҂�����ƂŊŎ���� |
|
| �����F �֘A�L���Љ�͂����炩�� |
|
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F �s���̗� turba mentis vigor meus |
No.B149027 NDC914.6 |
|
| ���ҁE�o�ŎЁF �ܖ؊��V/�W�p�� |
����2003/05/30 \1300 |
|
| ���e�F �v�����[�O �ڂ��͂���Ȃӂ��ɕs�����Ă��� �s���͋��낵�����̂ł͂Ȃ� �����g���ォ��t���ɂ�����s�� �����̕s���ɂƂ�͂܂�Ȃ��� �ق� �P�@���܁A�������������s�� �S�����Ȃɒʂ��������� �O����͌����Ȃ��u������̕s���R�v �s���͐l�Ԃ��x����厖�ȗ� �Q�@�u������̐푈�v�ɏ����Ă��܂��s�� �u������̐푈�v�ŏ������E�Ɍ������l�т� �������Ƃ�������ނ��邱�Ƃ�����Ǝv�� �ق� �R�@�Ⴓ�������Ă������Ƃւ̕s�� �ꌳ�I�ȕ����̕n���� �Ⴓ�����ł͂Ȃ����n�̖��͂ɂ������ �ق� �S�@�^�ɗ�����̂����ĂȂ��s�� �M������̂������Ƃ̋��� �@���Ƃ��������Ȃ����E�̈Ӗ� �����m�˂���V�����a���̎���� �T�@����ɂƂ�c����邱�Ƃւ̕s�� �A�i���O�̌����ƃf�W�^���ً̈�� �ق� �U�@�\�����邩������Ȃ������ւ̕s�� ����Ȃ�����ǂ��߂����� �����ɂ����������u�Ԃ������~��� �ق� �V�@�����ꏊ��������Ȃ��s�� �����ɉ����ł��邩�����ɂ߂� �ق� �W�@�a�C�Ǝ��̉e�ɂ��т���s�� �s�𗝂Ȏ��Ƃ������̂ւ̋��� ���ƒ��ʂ��邱�ƂŐ��������ł��� ���̐��ł����ЂƂ�̑��݂ł��鎩�� �X�@���ׂĂ��M�����Ȃ����Ƃ̕s�� �݂������āA�݂�Ȃ����A�̐��E ���Ő��܂�Ă��āA���Ŏ���ōs�� �P�O �{���̎�����������Ȃ��s�� �{���ɑ�Ȃ��Ƃ͓��ɉB����Ă��� �G�s���[�O�@�s������苭��������͂Ƃ��邽�߂� ���Ƃ��� �ܖ؊��V�m�C�c�L�q�����L�n �P�X�R�Q�i���a�V�j�N�X���A���������܂�B����Ԃ��Ȃ����Ē��N�����ɓn��A'�S�V�N�Ɉ��g����B����c��w���w���I���ȂɊw�ԁB���̌�A�o�q���ҏW�A�쎌�ƁA���|���C�^�[���o�āA'�U�U�N�Ɂw������X�N����A���x�ő�U������V�l�܁A'�U�V�N�Ɂw�����߂��n������x�ő�T�U�؏�܁B'�V�U�N�w�t�̖�x�ŋg��p�����w�܂���܁B���݂܂ŏ����A�]�_�A�G�b�Z�C�ƕ��L�����슈���𑱂��A���̕���͕��w�A���y�A���p�A�����܂ő���ɓn��B������̒����������s���Ƃ炦�A�u�v�̗��ꂩ��̌����ӂ܂������R�œƓ��Ȕ��z�͑����̓ǎ҂��䂫���Ă����B�܂��A�ߔN�͏@���Ɩ����𒆐S�ɂ����e�[�}���ڗ��B��\��́A�����Ɂw�����߂̖�x�E�w���̉����x�A�]�_��G�b�Z�C�ł́w���ɐ�����āx�E�w������q���g�x�V���[�Y�E�w��͂̈�H�x�E�w���́x�E�w���{�l�̂�����x�V���[�Y�E�w�S������x�V���[�Y�A�܂��@�@�Ɋւ��鏬���A�G�b�Z�C�A����Ȃǒ��������B |
||
| �����F �G�s���[�O���ꕔ����
|
||
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F ����łȂ������鎍�l |
No. B149024 NDC 911.520 |
| ����/�o�ŎЁF �k����/�v���� |
����2001/03/01 \2600 |
| ���e�F
���̖{�ɓo�ꂷ��\�O�l�̎��l�́A�u�ǔ����w�܁v����܂��ēV�����܂��Ƃ��������l�������A��\��̏I��ɗ]����N�Ƃ����݊��̐鍐�����������l���͂��߁A�a��ɔƂ��ꂽ��A���݂������Ď��E�����肵���ЂƂ��肾�B�u�Ȃ��œ|�ꂽ���K�Ȏ��l�����̉Ս��Ȑ������������܂�H��Ȃ���A���҂͂��������z���t�̂悤�ɁA����Ȃ���݂�����s���̎��I����������Ă�܂Ȃ��B�ِF�̎��l�_�B �i�ˍK�i �\���͑D����s�A�j�X�g�ł���ׂ������� �������� �\�K������{���C�f�}���l���Y�����f�c �V�쒉 �\�݂��Ȃ������c�̏�� �����F�� �\��Ȃ��Ƃ͊������ɂǂ��������ł͂Ȃ��ł��傤�� ���Ǖ����Y�\�����Ȃ��Ă�������ł��̂������܂���ď����̂ł� �X���֎q �\�u�����h�����R���炵�R���炵 �����O�v �\�c�ɂ̐e�������֗���� ��M�Y �\������Ȃ�����^�K�Ȃ͂��� �J��H �\�o�s���Ō�����ň��M�ʼn������Ẳ������̂悤�Ɉ��������� ����q �\�̂�ׂ��������B�킪�܂܂������B�₳���������B �{������ �\���������Ƃ����s�ׂ͎��̗\�s���K�ł��� ������Y �\�A�E�g�T�C�_�[���낤�ƃ~�c���T�C�_�[���낤�� �����u �\�g���͗g���킩�߂͂킩�߂̖������� |
|
| �����F DV,���t,�o������ |
|
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F �V���V�� ���ʂ��߂̋��{ |
No. B149023 NDC 910.268 |
| ����/�o�ŎЁF ���R���O�Y/�V���� |
����2003/04/10 \680 |
| ���e�F
���̋��|���瓦��邽�߂̍ő�̏���Ⳃ������@�����͂����������A�u�����̎����Ɏ����v���߂ɕK�v�Ȃ��̂́A�u���{�v�����ł���B�P�Ȃ�m���ł͂Ȃ��A�u���ʂ��߂̋��{�v�������A�u���Ȃ̏I���v��[�����邽�߂̕���ƂȂ�̂��B�ܓx�����ɂ��������҂��A�F���_���瓬�a�L�܂Ŏl�\�Z�������I�I���ꂪ�A�u���v�����Ȃ̂��̂Ƃ��Ď���鋳�{�ł���B �͂��߂Ɂ@�@�Ȃ��u���ʂ��߂̋��{�v���K�v�� ��P�́@��㔪���N�A�l�\�܍B���܂�ď��߂Ă̓f�� �@�@����f�������x���ᎀ�˂Ȃ��i�w�~�j���R���J��Ղ̐��ҁx�j �@�@���Ƃ��Ă̎������A���邢�͐����Ƃ��Ă̎������i�w�����߂���Θb�x�j �@�@�������̂悤�Ƀu���K�N�I�ɂ߂͐L�т₵�܂���i�w���̕����x�j�@�@�ق� ��Q�́@�����N�A�\�B�l������x�`�����ɂ��� �@�@�S���Ȃ�ė͎m�ɂ͋����Ȃ��i�w�l�ԁ@���̖��m�Ȃ���́x�j �@�@�m�Ԃ��Ō�ɂ��ǂ蒅�����̂́A�u��]�v�i�w�m�Ԃ̗U�f�x�j�@�ق� ��R�́@���l�ܔN�A�O�B���߂Ď��ɂ����� �@�@��Ƃ����������̂͂��ׂāA�����Ƃ����`���肽�⏑�ł���i�w�L�`�̊C�x�j �@�@��[�N���̏����ɂ��܂肭��l�Ԃ̎��i�w�R�̉��x�j �@�@�l�Ԃ����B�ɂ���Ď����u��������v�͕̂s�\�ł���i�w���ƈ��x�j �@�@���Ƃ����������A�Ӗ�������́i�w���̓��{���w�j�x�j �@�@�u�����̔�V���Ƒ��g�����v���āH�i�w���Ǝ��̃R�X���O���t�B�[�x�j�@�@�ق� ��S�́@���㔪�N�A�\�Z�B�ӂ����ь������f�� �@�@�������A�����Ă������̂��i�w�吼�m�Y���V�U���ԁx�j �@�@���ʂƂ��́A�݂�Ȉ�l�i�w��������l�̐��ҁx�j �@�@���́A����ƃG���e�B�b�N�Ȋ�����������Ă�i�w�l�Ԃ炵�����ɂ����x�j �@�@�ǂ�����Ď���ł������炢���̂��낤���i�w�]���������̗D��ȃT���i���x�j �@�@�����ɑ����̐l����C�ɂ���������i�w��C�̕��i�x�j �@�@���ɂ䂭��ɉ����ł���̂��A�l�ɂƂ��Ď��Ƃ͉����i�w�����₩�Ȏ��x�j�@�ق� ��T�́@��Z�Z��N�A�\��B�^�N�V�[�ɏ���Č�ʎ��� �@�@�l�̈ꐶ�����̗��j����̗���Ɠ����i�w���{�l�̎����ρx�j �@�@�⑰�ɂ́A�����߂��݂��҂��Ă���i�w���ʏu�ԁx�j �@�@�{�����@�،o�ɂ������Ă����i�w�{���u�J�j���}�P�Y�v�蒠�����x�j �@�@����������m���ꂽ�Ƃ��A���҂͂ǂ��l���邩�i�w���Ҋw�x�j �@�@���E��]�́A���̂��N�����₷���X�������߂�i�w�������T�x�j �@�@���Ŏ����̎���̐��E����������i�w���̎����ρx�j �@�@���ɂƂ��ďd�v�Ȗ�Ƃ́i�w�n���͍����ł���x�j �@�@�䕚����̂悤�ɐ����Ă݂����i�w�җ�̌�x�j�@�ق� ���R���O�Y�m�A���V���}�R�E�U�u���E�n �P�X�S�Q�i���a�P�V�j�N�É������܂�B��ƁB���w�@��w�����ȑ��A���}�Г��ЁB�O�\���ŎG���w���z�x�ҏW�����Ō�ɑގЁA�Ɨ��B�����Ɂw�f�l�����L�x�i�u�k�ЃG�b�Z�C�܁j�A�w�m�Ԃ̗U�f�x�i�i�s�a�I�s���w��܁j�ȂǁB�ŋ߂́A���{�̋ߑ㕶�w��V�������_�ő�������i����|���Ă���B |
|
| �����F ���A���E�A���� |
|
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F �V���V�� ���S�L����ǂ� |
No. B149022 NDC 70.180 |
| ����/�o�ŎЁF �����B��/�V���� |
����2003/06/20 \680 |
| ���e�F
�����ɂ͐l�Ԃ̃h���}������B������w�ɓO����A�������\���s�̋L���ł��A���̈���ꂪ���[���B�Ėڟ�����i�n�ɑ��Y�܂ŁA���w�҂̎��͂����ɕ��Ă������B�|�\�l�͂Ȃ��o�J�ł����L���ɂȂ�̂��B�o�ϐl��싅�I��̈����͋Ɛтɔ䂵�ď������B���O�̉E�ɖT�����������R���́B��h�̎Љ�ʂ͌��o���ŏ����B�c�N���������ڂɂ��Ȃ���A���͒m���Ă��Ȃ����̓ǂݕ��B �� �́@���������������l�O�l�̎� ��P�́@�����ȏ������]��ɖ������� ��Q�́@��ʂ���ΊW�Ҍ^�ƒm���x�^ ��R�́@���w�҂Ɍ���S�N�̕ϑJ ��S�́@�Ȃ��|�\�l�̈����̓o�J�ł����Ȃ�̂� ��T�́@���v���싅�I��͎₵�� ��U�́@�`���u�����ȕʏ��v�������� ��V�́@���o���ɕҏW�L�҂̋�Ⴀ�� ��W�́@���������ƎO�V���~���ł͂ǂ������̂��I ��X�́@�q�b�ƃA�C�f�B�A�œǂ܂���L���ɂȂ� �I�́@�V���Ђ́u���S�L�����v��ݒu���� �����B��m�����I�J�^�c�C�`�n �P�X�R�U�i���a�P�P�j�N�����s���܂�B�R�����j�X�g�A���S�L���A�i���X�g�B������w�����o�ϊw�����ƁB�������V���L�ҁB���݁A�u�싅�����w��v�����ǒ��Ƃ��Ę_�p�u�x�[�X�{�[���W�[�v�̊��s�ɐs�́B |
|
| �����F |
|
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F ��������`�������ʂꂩ��̏o�� |
No.B149019 NDC914.600 |
| ����/�o�ŎЁF �L���N�m���t�H��y�ҁz/�@���� |
����2001/12/10 \1300 |
| ���e�F
���Ǝ��A�o��ƕʂ��ʂ��Ă��̂������߂��l�ԃh���}�Q�V�сB�L���̐N�����҂̌Ăт����ɉ����S�������ꂽ�A���L������̌�����{�l�̂�����͗l��m��i�D�̃G�b�Z�C�W�B �������̂������߂Ȃ������������ɁE�E�E���� �@���̂��𗝘_�◝���݂̂Ō��̂ł͂Ȃ��A�u�ʂꂩ��̏o���v�Ƃ����N�����o��������̌���ʂ��āA���̂������߂Ȃ������Ƃ��ł��鎋�_�����Ă�A�Ƃ����肢���炱�̊�悪�n�܂�܂����B ��N�O�̓�Z�Z�Z�N�H����A�u��������`�������ʂꂩ��̏o���v�Ƃ����e�[�}�ōL�����e���W�����Ƃ���A�S������l���Z�ʂ��̌��e�����܂����B �����͂��̂��Ƃ����傫�Ȗ����O�Ɉ�𓊂������ƍ\���Ă����킽�������ɁA���̌���ʂ��Ă̖c��Ȑ��́g���̂��̓��e�h�����������A�ǂނɂ�āA�t�ɑ����̂��Ƃ������������܂����B �R�R���\��̂Ђ� �g���l���\�o���� �\�E�}�g�E�\���� �V�R���\���܂ł� �q�L�R���S���\���̑I�� �I���J�Q�\���Ɖe |
|
| �����F �L���N�m���t�H��̃T�C�g�Љ�͂����� �u��������`�������ʂꂩ��̏o���v���e��i480�ʓ��� |
|
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F ���t�V�� ��c�R���̎��� �ق�ق�ق�т䂭 |
No.B149018 NDC911.360 |
| ����/�o�ŎЁF �n�ӗ��v/���|�t�H |
����1998/10/20 \640 |
| ���e�F
���ɓM��A�Ƃ��̂āA�S�����s����o�l�R���B�f��Z�\�N�A���̋�͂܂��܂������̋����Ă���B�����痷�ւ̐l���B�������ނ͒P�Ȃ�Y���̎��R�l�������̂��H�ہB�c�����Ɍ������̕����A��̎��فA�ƎY�̊����c�B�������Ƃ�܂����ׂĂ��łт䂭�Ƃ̋����ϔO�ɂ����Ȃ܂�A�o�������߂Â����_�o�ǎ҂̕K���̓f�I���ނ̋傾�����B�i�N�R�����g�S�̗F�h�Ƃ��Ă����A�W�A�o�Ϙ_�̑��l�҂��A���̐��U�Ɠ��ʂ̋�Y�ɓ�������B�Ȃ��ނ̋傪����l�̐S��h���Ԃ�̂��B�����ނ����ēD���Ɨ��]�ɒǂ����Ă��̂��B�Y���̔o�l�̐��U�Ƌ�Y��`���ِF�̎R���Α� ���� �� �S���т��� �y�ɋ�Ђ��� ���� ���̗��A�ʂĂ��Ȃ� ���Ƃ̏t ���� �����Ђ������Ƃ͂Ȃ� �قق�����ۂ� ���납�ȏH�� �_�֕��� �n�ӗ��v�m���^�i�x�g�V�I�n �P�X�R�X�N�b�{�s�ɐ��܂��B�P�X�U�R�N�c���`�m��w�o�ϊw�����ƁB�P�X�V�O�N����w��w�@���m�ے��C���B�o�ϊw���m�B�}�g��w�����A�����H�Ƒ�w�������C�B���݁A��B��w���ۊJ���w�������E�w�����B�����H�Ƒ�w���_�����B�����Ɂw�����̃A�W�A��̃A�W�A�x���m�o�ϐV��ЁA�P�X�W�T�N�i�g��쑢�܁j�A�w�J���o�ϊw�x���{�]�_�ЁA�P�X�W�U�N�i�啽���F�L�O�܁j�B�w�������m�̎���x���|�t�H�A�P�X�W�X�N�i�A�W�A�����m�ܑ�܁j�A�w�_�o�ǂ̎���x�s�a�r�u���^�j�J�A�P�X�X�U�N�i�J�����ܐ��܁j�A�w�J���o�ϊw����x���m�o�ϐV��ЁA�Q�O�O�P�N�A���B |
|
| �����F ���R���A�o��A������� |
|
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F ����ʂ��Đ����l���鋳�� �q�������̌��₩�Ȗ������߂����� |
No.B149015 NDC375.000 |
| ����/�o�ŎЁF �������u�y�Ғ��z/�쓇���X |
����2003/02/20 \2200 |
| ���e�F �ŋ߂́A�q�������ɂ���Ĉ����N������鐔�����̐M�����Ȃ��悤�Ȏc���Ȏ����̔w�i��T��A���܂�ɂ����̑��݂����̏d�v�����m��Ȃ����邱�Ƃ��킩��B�{���́A���Ɛ��̖���[���l�@����Ƌ��ɁA����������̌���ŋ����E���t�����邱�Ƃ̓�����z���Ď��g��ł��������H�̋L�^���܂Ƃ߂����́B�q�������̖��邢�����̂��߁A���̋���i�f�X�E�G�f���P�[�V�����j�ɊS�����l�����A�L���w�Z����̏�����Ă������ƍl����l�����ɂƂ��čœK�̎w�j�ƂȂ���̂ł���B ��P�́@���Ȃ��g����ʂ��Đ����l���鋳��h���K�v�� ��Q�́@�f�X�E�G�f���P�[�V�����̌����\��������ь��ʂ̕��͂ƍl�@ ��R�́@�o�[�`�����E���A���e�B�Ǝ��Ƃ̊֘A�\�����Ƃ��̌������� ��S�́@�f�X�E�G�f���P�[�V�����̎��ہ\���w�Z�E���w�Z�E���Z�ł̎��g�� ��T�́@����r�f�I�̐���ƁA���̃r�f�I������������̊��z�� ��U�́@�w����ʂ��Đ����l���鋳��x���M�ҍ��k�� �������u�m�i�J�����q���V�n �����s�o�g�B�P�X�U�Q�N���{��w��w�����ƁB�P�X�V�S�N����w��w�������Ȑ�C�u�t�B�P�X�W�O�N�d�ǎ��{�݁u�ނ炳�����牀�v�����B�P�X�W�Q�N���{��w�q�������B���N�����×{�������a�@�@���B�P�X�X�T�N���{���q��w�Ɛ��w�������w�ȋ����B���݂Ɏ��� |
|
| �����F ���A�f�X�E�G�f���P�[�V���� |
|
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F �V������ �Ǔ��̒B�l |
No.B149011 NDC910.260 |
| ����/�o�ŎЁF ���R���O�Y/�V���� |
����2002/07/01 \819 |
| ���e�F
����ł��Ȃ��ꂽ���B����������Ȃ��������O�B�Ǔ��ɂ���Đ��ɏo���{���B�ՏI�̓c�R�ԑ܂Ɂu���ʋC���͂ǂ�Ȃ��̂��ˁv�Ɛu�˂����蓡���c���ɂ܂��G�s�\�[�h�́A�����Ƃ̐��g�̎p��N�₩�ɕ�������ɂ���B���l�����͒m�l�̎����ǂ������A�ǂ��\�������̂��H�����A�吳�A���a�̕��m�l�\��l�̎��Ɋ�ꂽ����Ǔ����⒢����ʂ��āA�ߑ㕶�w�̐V���Ȉ�ʂ����B ���� �����q�K�\����ŕS�]�̋�ƂȂ� ����g�t�\�e���͈����� ���_�\�����܂��u���k�v �����R�E���ؓc�ƕ��E��t���l���E�ΐ��� �吳 ��c�q�\�����ɍs���Ȃ����R �Ėڟ��\�������Ȃ����l�X ���A�\���傤�ǎ��ɂ��� �X���O�E�L�����Y�E��c���A ���a �H�열�V��\�u��������A�悩�����ł��ˁv ��R�q���\�A�������҂𐬕������� ���R���O�\���҂͎��l�ɂ������ ���c�D���E�ݓc�����E�c�R�ԑ܁E���ё����E�ޒJ���g�E �|�v����E�ؓ�疗y�E�^�Ӗ�S���E��؎O�d�g�E ��������E���{���̎q�E�ԁE�����Y�E�^�Ӗ쏻�q�E �k�����H�E���蓡���E�K�c�I���E��������E ���Ɏ��E�ѕ����q�E�֓��g�E�x�C�Y�E���������Y�E �i��ו��E�Ζ숯���E���c���j�E�J�菁��Y�E �O���R�I�v�E�u�꒼�ƁE��[�N���E���ҏ��H���āE���яG�Y �i����11�N12���V���Њ��s�̒P�s�{�ɉ��M�j ���R���O�Y�m�A���V���}�R�E�U�u���E�n �P�X�S�Q�i���a�P�V�j�N�A�É�������B�G���ҏW�҂��o�āA��Ɗ����ɓ���B�f�W�W�N�A�w�f�l�����L�x�ɂ��A�u�k�ЃG�b�Z�C�܂���܁B���݂́A�ߑ���{�̕��w�҂������A�l�X�Ȑ�����瑨���Ȃ������Ƃ��A�e�[�}�Ƃ��Ă��� |
|
�����F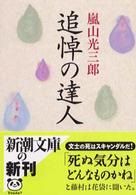 |
|
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F ���ؑI�� �Q ���V�a���̋���� �����ƐS���Ö@ |
No.B149010 NDC180.400 |
| ���ҁE�o�ŎЁF ���s���؏��q��w�^�@�����������A���c���j�A��{�b�q�A���������A�V������/���ƎЏo�� |
���� 2001/04 ��2,520 |
| ���e�F �܂����� ���؏G�� ���� ����̃��C�t�T�C�N���ƕ����̎����� �c���c���j �t���C�g���烆���O�ւ̃��C�t�T�C�N�����_ �����Ɍ��鎀�ƍĐ� �ق� ���� �q���ƈيE�c��{�b�q �يE�Ƃ͂ǂ��������E�Ȃ̂� ��A���v�X�̏����n�C�W��Ɍ���يE �ق� ��O�� �����k�����ρc�������� �������߂����� �����Ə@�� ���R�@���Ƒn���@�� �����Ɛ��� �����̎Љ�I�`���_ ����ɂ����鐫�� ���{�����Ɛ��� ��C�O���̐����� ��l�� ���N���̏����ƕ����c�V������ �߉ނƔY�� �����Ƃ̑Θb �����O�Ǝ߉ނ̏ꍇ �ق� ��� �����}����c�������� �����ǂ̂悤�ɍl���邩 �����w���x�Ɍ���{���̐������Ƃ� �Ėڟ��ɂ����鎩�R�Ƃ̈�̊� �w�t���ς̃t���f�B�x�Ƌ{�����b���`�����E�̈Ⴂ �ق� �`���I�ȐM�ɂ����鎀 �w�V�ُ��x�ɂ݂�~�ς̌��� ��Z�� �^�@�̎����ρc���c���j ��߈��̎d����Ƃ��Ă̢�����̎����ϣ�̈Ӗ� ���Ɏ��̐S�̗� ��敧���̐l�Ԋ� ���̗��z�I�l�ԑ� �^�@�̎����� �^�@�̐l�Ԋ� ��y���̖{�` |
�����F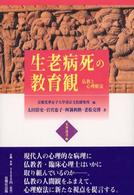 |
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F �t���� �l�Ԃ͂ǂ�����Ď���ł����̂� �g�ݍ��܂ꂽ�u���̃v���O�����v�̓� |
No.B149008 NDC491.358 |
| ���ҁE�o�ŎЁF �ĎR���[/�t�o�Ŏ� |
���� 2002/03/20 \514 |
| ���e�F �{���́A���S���v�ɉB�ꂽ�����̌���������A�����̏I���̓�Ɏ��g����ł���B ���́@���̂Q���ԑO�A���̂Q���O ����l���|�ɐU���Ȃ����߂� �ق� �P�́@�ǂ�������Ɛl�Ԃ͎��ʂ̂� �\�����������Ō��A���X�ɐi�s���鎀�c�A���ɕ������߂�v���� �]�ً̋}���� �S���͂������Ď~�܂� �x�E�ċz��̒�~�@ �ق� �Q�́@���ׂŎ��ʂƂ��A����Ő������т�Ƃ� �\�����A���a�A�i�s�A�I���c�A�a�C�̂����Ő����͕������ ����Ŏ���ł���̂� ���A�a�Ŗ��𗎂Ƃ��Ƃ� �Q�����芳�҂����ʂ܂� �V���Ƃ����s�v�c�Ȏ� �@�ق� �R�́@�l�����ʗ��R�A�����鉿�l �\���̃v���O�����́A�Ȃ��g�ݍ��܂�A����������̂� �l�̎����͉��Ō��܂邩 �{���Ɏ��͕K�v�Ȃ̂� ���̒�` �����ǂ�����邩 ����ł��l�Ԃ��������т鉿�l �@�ق� ���������a�C�E�Ǐ�ʍ��� �R���� �����瓦��邽�߂̍ŐV�Z�p �A�W�A�l�͂���Ŏ��ɂɂ��� ���S���͂�������Ό���B �i1999�N�ɐt�o�ł�芧�s���ꂽ��i�ɉ��M�������ꂽ���́j �ĎR���[�m���l���}�L�~�q���n �P�X�T�Q�N�R�������܂�B��w���m�B ���͐_�o���ȁB�Տ���Ƃ��đ����̊��҂̎��Âɂ�����Ȃ���A�G�b�Z�C�A�~�X�e���[�A���p���Ȃǂ̎��M��������A�u���A�e���r�E���W�I���̏o���ȂǁA���L�������͓I�ɍs���Ă���B �����F |
|
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F �V���� ���̏��� |
No.B149006 NDC114.200 |
| ���ҁE�o�ŎЁF �ߓ����A���_���A�R�c����A�g�{�����A���������q�A�X��a�]�A���_���A��������A���l��Y�A���n�L�s�A�����/�m��� |
���� 2001/07/21 \700 |
| ���e�F �ӂƁu���v���悬��̂͂ǂ������Ƃ����H�l�Ԃ͂��Ȃ炸���ʁB������l�̗�O���Ȃ��B�����A���͒ʉߓ_�ł͂Ȃ��A�ӂ肩�����ĉ�ڂł�����̂ł��Ȃ��B����ЂƂ�Ƃ��Ď����o���ł����A�䂦�Ɏ��̌o���������Ȃ��B����ł��A�l�́u�����̎��v�ɂ��čl����Ƃ�������B�u���̒N�ł��Ȃ��A�����̎����ǂ��l��������̂��B���̎��̏����̂��߂Ɂv���̌Â��ĐV�����e�[�}���A���܂��܂ȃW�������Ŋ������̏\���̒��҂����ꂼ��Ɂu���̎��v�ɂ��Č��B �P�@���̏����Ƃ͂Ȃɂ� ���̎�O�̎��i�R�c����j ���̏����Ƃ͂����ЂƂA���̂��Ƃ��o�傷�邱�Ɓi�����^���q�j �����}����S�̏����Ȃ�ĉʂ����Ă���̂��i�g�{�����j �Q�@���Ƃǂ����������� �����u����v�ɜ������i�ߓ����j �{���̕a����m�� ���Ö@�͎����ōl�������Ō��߂� ���Ö@��I�����邽�߂̂킽���̎��_ ��̓I�ȑΏ��@�B�\�]�ڊ��̏ꍇ ����Ŏ����}���邽�߂̏��� �ق� ���ɂ��āi��������j ���͂ǂ��܂ł������̎��ł���A���l�̎��ł͂Ȃ� ��a�����m��͂����Ă]�����m��͂����Ă͂Ȃ�Ȃ� ���������ł���Ƃ������| ����̐��E�̋~�ς����߂Ȃ��ԓx �����F���ƂȂ�ɂ͉����K�v�� �ق� ���ɂȂ肽��A�R�̕����̕��i�X��a�]�j �q�ǂ������ց\���҂͐���������i���_���j �R�@����m��Ƃ͂ǂ��������Ƃ� ���͐����m�肷������ł���i���l��Y�j �����}���鎀�i���n�L�s�j ���Ƃ������M�i�����j �ߓ����m�R���h�E�}�R�g�n �P�X�S�W�N�������܂�B�c���`�m��w��w�����ƁB���݁A����w��w�����ː��ȍu�t ���_���m�q�K�L�^�J�V�n �P�X�T�W�N���쌧���܂�B���k��w�@�w�����ƁB��ƁE�W���[�i���X�g �R�c����m���}�_�^�C�`�n �P�X�R�S�N�������܂�B����c��w����w�����ƁB�r�{�ƁE��� �g�{�����m���V���g�^�J�A�L�n �P�X�Q�S�N�������܂�B�����H�Ƒ�w���ƁB���l�E��]�� �����F |
|
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F �l�ԗՏI�}���q�R�r �k���y�Łl |
No.B149003 NDC280.000 |
| ���ҁE�o�ŎЁF �R�c�����Y/���ԏ��X |
����1996/12/31 ��1,528 |
| ���e�F �V�R�`�P�Q�P�Ŏ��l�X�B�����\�l���̔N�ւ�������d�˂Ă��𖾂���Ȃ����ƁB���ꂪ���ł���B�l�ނɂƂ��āA�����Ƃ��d�傩�i���̃e�[�}�ł��鎀�ƁA���̋O�Ղ������ɂ���B �R�㉯�� �J�U�m���@ �ɔ\���h �NJ� �O�����E�� �֓����Y �_�[�E�B�� �������Y�� �p�X�g�D�[�� ���{��M �͖{��� ���������Y �����Ґ� �ق� �����F |
|
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F �l�ԗՏI�}���q�Q�r �k���y�Łl |
No.B149002 NDC280.000 |
| ���ҁE�o�ŎЁF �R�c�����Y/���ԏ��X |
����1996/11/30 ��1,528 |
| ���e�F �T�U�\�V�Q�Ŏ��l�X�B�l���ɂ����ėB��A�N�ɂ��o���o���Ȃ����ƁB���ꂪ���ł���B���ɌŎ����邩�A���J�̒��ɐ����̂��B�l���̂��ׂĂ��g���̏u�ԁh�ɋÏk����Ă���\�B�H��̖������y�ŁB �\�Z�Ŏ��l�X �_���e�G���q���G�G�O�Y�j�@�ق� �\���Ŏ��l�X �x�[�g�[���F���G���쒉�M�G�p�[�N�X�@�ق� �\���Ŏ��l�X �V�[�U�[�G�m��G�������^�@�ق� �\��Ŏ��l�X �i�n�J�G�����e�[�j���G�N�����E�G���@�ق� �Z�\�Ŏ��l�X �W���M�X�J���G���@�G�R�����u�X�@�ق� �Z�\��Ŏ��l�X �}�z���b�g�G�����G��C�@�ق� �����F |
|
�ژ^�ɂ��ǂ�
| �����F �l�ԗՏI�}���q�P�r �k���y�Łl |
No.B149001 NDC280.000 |
| ���ҁE�o�ŎЁF �R�c�����Y/���ԏ��X |
����1996/10/31 ��1,528 |
| ���e�F �P�T�]�T�T�Ŏ��l�X�B�l�͒N�ł�����|���B��������A�Ƃ͂킩���Ă��Ă��A���ꂪ�g���h���Ƃ͒N���M�������Ȃ����̂��B�Ⴍ���Đ���S�������҂����̍Ŋ��̍��B�s���̖��앁�y�ŁB �\��Ŏ��l�X ��\��Ŏ��l�X �O�\�Ŏ��l�X �O�\��Ŏ��l�X �O�\��Ŏ��l�X �O�\�O�Ŏ��l�X �O�\�l�Ŏ��l�X �O�\�܍Ŏ��l�X �O�\�Z�Ŏ��l�X �O�\���Ŏ��l�X �ق� |
�����F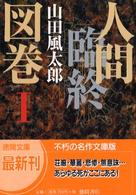 |
�ژ^�ɂ��ǂ�